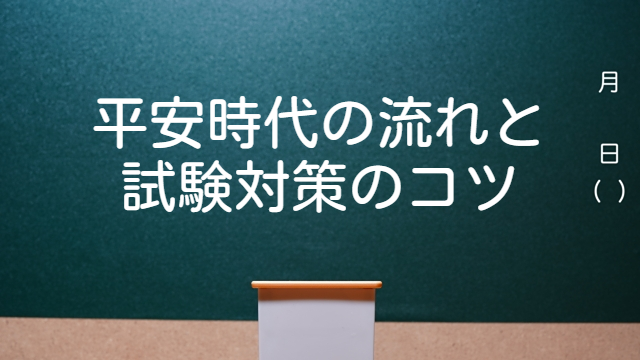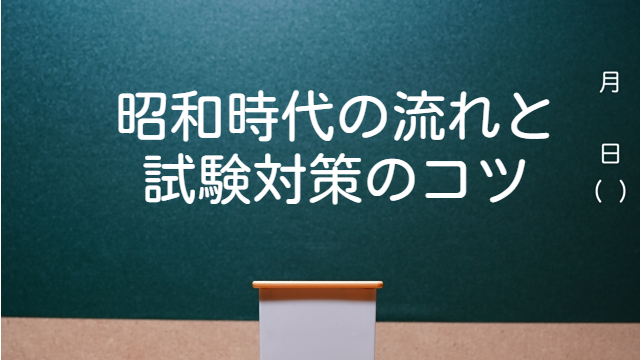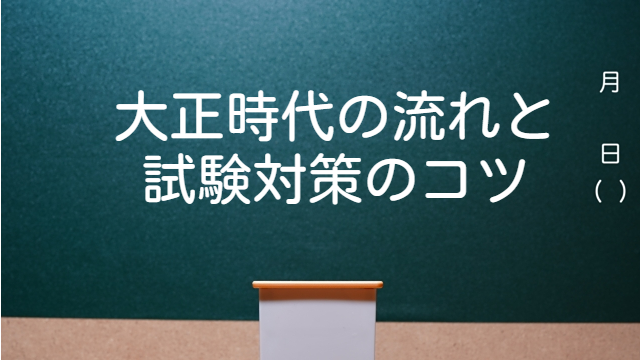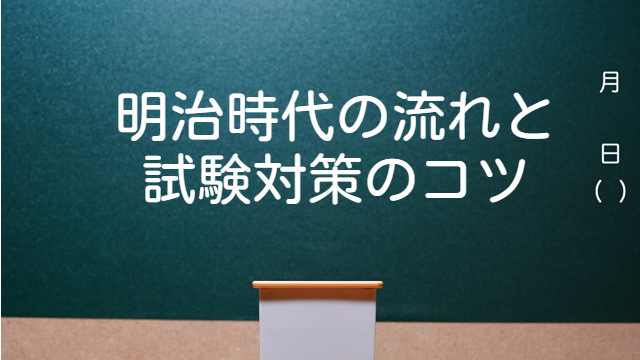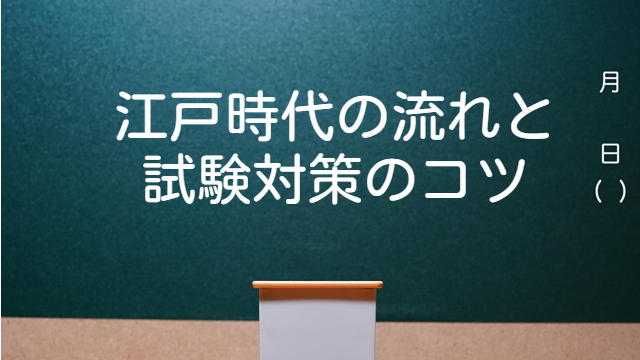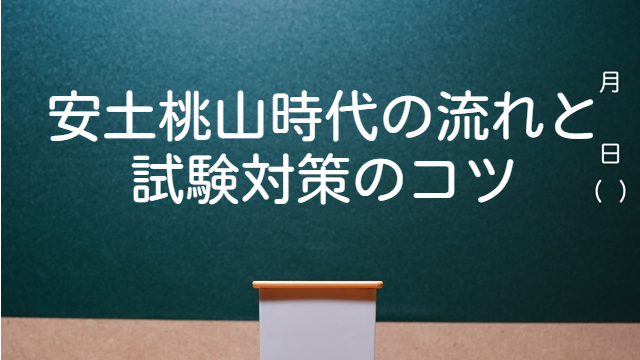794年の桓武天皇(かんむてんのう)の時代に、日本の都は平安京に移ります。
ここからおよそ300年にわたる平安時代が始まります。
この時代には権力が藤原氏を中心とする貴族の手に渡り、政治の仕組みや地方行政にも大きな変化が生まれました。
期間が長い時代区分なので、年表を作り年代順にできごとや登場人物を整理しておくとよいでしょう。
この記事の内容
藤原氏と貴族政治
平安時代の初期はまだ天皇もある程度の権力を持っており、平安京の造営と東北地方の平定という2つの大事業を指揮していました。
しかし平安京に遷都する前後に、またもや皇族内での権力争いが激化して、天皇家は政治をコントロールする力を失います。
代わって政権を担うことになるのが藤原氏ですが、完全に権力を握ったのは9世紀の後半になってからでした。
この時に藤原良房(ふじわら の よしふさ)が初めて摂政(せっしょう)に任命され、その後任の藤原基経( ふじわら の もとつね ) が関白(かんぱく)に任じられました。
ここからが摂関政治(せっかんせいじ)の始まりです。
摂政とは幼い天皇に代わって政治を行う地位であり、天皇の成人後に政治の補佐をするのが関白です。
それからおよそ150年を経て、藤原道長(ふじわら の みちなが)と藤原頼通(ふじわら の よりみち)の時代に貴族政治はピークを迎えます。
ちょうど西暦1000年ごろのことなので、歴史上のチェックポイントとして覚えておきましょう。
この後100年近く、摂関政治は道長の家系によって独占されます。
平安時代の地方政治
それまでの国司による地方統制は、平安時代に徐々に変化します。
政府は国家財政が苦しくなったため、国司の徴税権を強化しますが、国司が地方からの税収の一部を私有化するようになり、国の経営は苦しいままでした。
このころの国司を受領(ずりょう)とも呼びます。
国司は貴族の中から選ばれたため、結局貴族に富が集中するようになり、天皇家を中心とする皇族の収入は減少を続けます。
さらに地方での土地制度も機能しなくなり、有力貴族は荘園経営によりさらに富を増やします。

荘園などの土地制度については当サイトの「【日本史勉強法】奈良時代の流れと試験対策のコツ」という別記事で詳しく説明しています。
墾田永年私財法により土地の私有が認められると、農民の間にも有力者が現れるようになりました。
彼らは税負担や国司の介入を免れるため、中央の貴族や寺社に土地を寄進して、事実上の経営者である荘官(しょうかん)という地位を得ます。
中央の有力貴族の荘園はますます肥大して、政府の財政はさらに苦しくなって行きます。
武士の登場と成長
10~11世紀になると、中央貴族の所有地である荘園や地方有力者の所有地などを警護するために武装集団が配備されるようになり、これが武士の起源だと言われています。
実際には中央から地方に派遣された貴族が土着して、さらに武装するようになった例もあるなど武士の誕生にはさまざまなケースがあったようです。
いずれにしても、当時の武士は貴族の配下として働く立場でしたが、10世紀半ばに貴族政治に衝撃を与える事件が起こります。
それが承平・天慶の乱(じょうへいてんぎょうのらん)であり、関東地方では平将門(たいら の まさかど)が、瀬戸内地方では藤原純友(ふじわら の すみとも)が、共に939年に政府に対する反乱を起こします。
どちらもすぐに平定されましたが、武士の成長を象徴するような事件でした。
東北地方の平定
平安時代は時の朝廷の勢力が、北海道を除く日本全土に及んだ時期でもあります。
特に平安初期の天皇は、東北地方を実質支配していた蝦夷(えみし)の討伐に力を入れており、9世紀初めには征夷大将軍に任命された坂上田村麻呂(さかのうえ の たむらまろ)が蝦夷の平定に成功しています。
しかし878年には蝦夷による大規模な反乱が起こります。
この元慶の乱(がんぎょうのらん)を治めたことで、ほぼ東北全土が朝廷の勢力下に置かれました。
再び東北地方が乱れ始めたのは11世紀半ばのことで、当時東北で勢力を拡大していた安部氏(あべし)と、朝廷が派遣した源頼義(みなもと の よりよし)とが武力衝突を起こしました。これが1,051年から始まった前九年の役(ぜんくねんのえき)です。
さらに1083年から始まった後三年の役(ごさんねんのえき)では、東北の有力者清原氏(きよはらうじ)の内紛を、頼義の子の源義家(みなもと の よしいえ)が鎮圧しました。
この2つの戦いにより、源氏は東国武士団をまとめる勢力にまで成長します。
平安時代の暮らしと文化
907年に中国で唐が滅亡したことから、日本では唐の文化を日本風にアレンジした国風文化(こくふうぶんか)が盛んになりました。
「古今和歌集(こきんわかしゅう)」「枕草子(まくらのそうし)」「源氏物語(げんじものがたり)」などがこの文化の代表です。
貴族の邸宅の寝殿造り(しんでんづくり)や、十二単(じゅうにひとえ)などの豪華な暮らしも頭に入れておきましょう。
また10世紀には仏教の一派として、「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」を唱えると極楽に行けるという阿弥陀信仰(あみだしんこう)が流行しました。
さらに11世紀の平安末期になると、仏教が衰退するという末法思想(まっぽうしそう)が広がり、社会不安が高まりました。
テストではここがポイント!
平安時代は、それぞれのできごとをバラバラに覚えると混乱が深まってしまいます。
そこで、貴族政治の移り変わりと、武士の成長という2つの軸を中心に歴史をまとめるとよいでしょう。
まずはこの2つの流れを理解してから、荘園制度やいくつかの戦乱などを関連づけて覚えることです。
また、天平文化~国風文化など、各時代で異なる文化が登場します。
覚えづらいとは思いますが、それぞれの文化の特徴をつかんでください。
その後で細かい書物名や人物名を覚えると効率的です。
まとめ
平安時代の中心的存在は貴族でしたが、時代の流れを見てみると、武士の活躍もかなり早い時期から始まっていたことが分かります。
ただし大きな戦いでは、中央から任命された貴族が指導者の地位に就くことが多く、武士の立場はまだまだ下でした。
それが前九年の役と後三年の役のころから変化し始め、東国では源氏が武士団をまとめる存在になり、同じころに西国では平氏の一族が勢力を伸ばし始めます。
やがてその2つの勢力がぶつかる時代になると、貴族政治は終わりを迎えて武士による政治が始まるのです。
受験生、学生、勉強をし直したい社会人の方へ
苦手なこと、一度習ったけどわすれてしまったこと、気になることがあった場合はすぐに学び直すことが重要です!最近では短時間・短期間で学び直しが出来るオンライン家庭教師が人気です。

当サイトでは初めてオンライン家庭教師を利用する方向けに、オンライン家庭教師の選び方を紹介する記事も掲載しておりますので是非ご覧ください!

次の時代を勉強したい方は当サイトのこちらの記事をお読みください ⇒
【日本史勉強法】鎌倉時代の流れと試験対策のコツ
前の時代を勉強したい方は当サイトのこちらの記事をお読みください ⇒
【日本史勉強法】飛鳥時代の流れと試験対策のコツ
最後までお読みいただきありがとうございました。