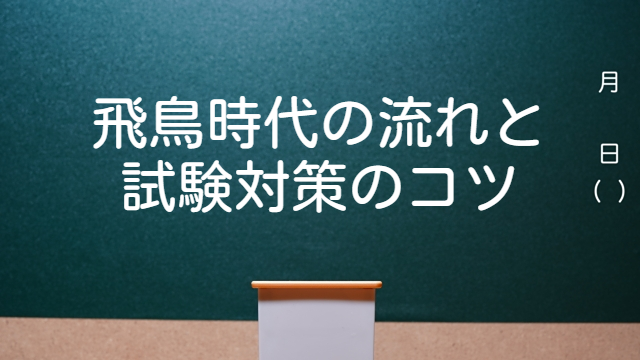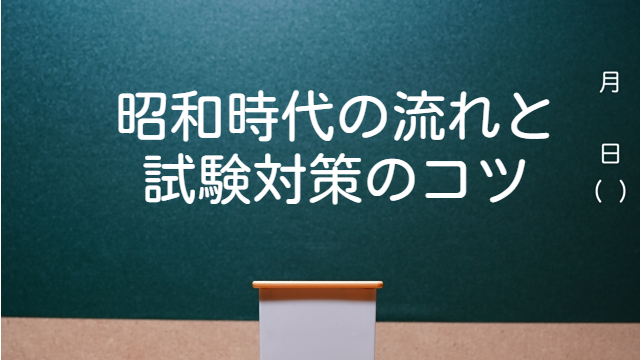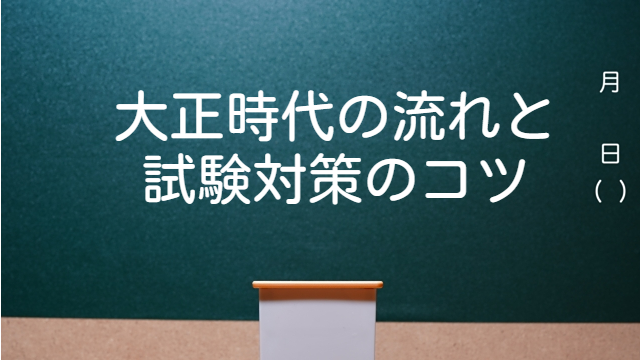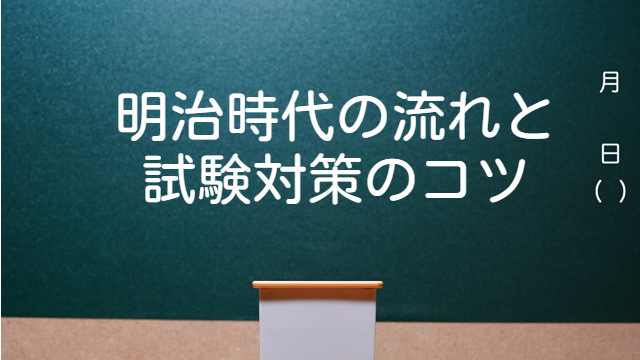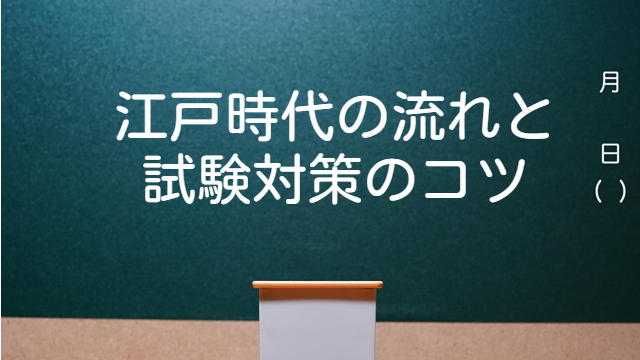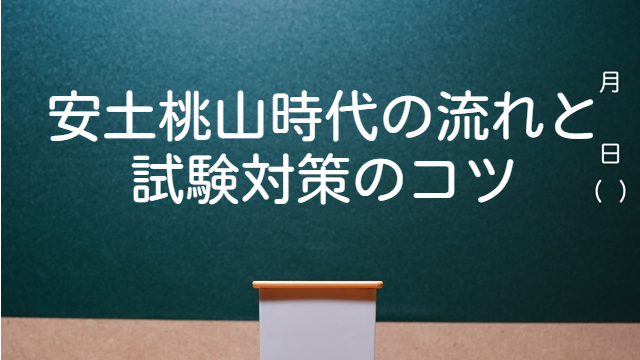日本古代史のモヤモヤが、だんだんと晴れてくるのがこの飛鳥時代です。
卑弥呼の次に登場する初期日本史を代表する有名人や、まさに歴史に残るできごとの中心になった人物が、はっきりとした姿で活躍する飛鳥時代。
実は他国との関係においても、国内情勢においても、非常にドラマチックな時代だったのです。
この記事の内容
飛鳥時代の概要をつかむ
ヤマト政権が成長するにつれ、今度は国外との関係も重要な課題になってきます。
6~7世紀には中国に隋(ずい)と唐(とう)という強大な統一国家が生まれたことで、周辺諸国は極めて大きな影響を受けました。
日本もこれらの国から、さまざまな文化や社会構造を受け入れることになります。
飛鳥時代の日本は、まるで明治維新のころのように、当時の超大国から先進的な仕組みを導入して、国家として成長する大きな時代の転換期にありました。
この時期は政治の形が整うと共に、天皇中心の国づくりがピークを迎えることになります。
当時の政権を支えた氏姓制度
この時代の政権は、氏姓(しせい)制度によって政治を行っていました。
氏(うじ)とは血縁関係をもとにした単位で、蘇我氏(そがうじ、そがし)や物部氏(もののべうじ)のような親族の集合体と考えればよいでしょう。
彼ら政権を担った人々は、大王に近い中央の有力豪族たちでした。
また氏とは別に姓(かばね)という単位もあり、中央の有力豪族には臣(おみ)、独自の職についた豪族には連(むらじ)という姓が与えられました。
この中で現在の大臣クラスの権力を持っていたのが、前述した蘇我氏や物部氏です。
地方政治は各地の有力豪族を国造(くにのみやつこ)に任じ、行政や税務は彼らを中心に行われました。
各地には大王の直轄領(私有地)である屯倉(みやけ)が設置され、大王の権力を支える役割を果たしました。
古代史最大のヒーロー聖徳太子の登場
6世紀の中ごろに初めて日本に仏教が伝来し、仏教擁護派の蘇我氏と反対派の物部氏との間で抗争が勃発、物部氏を滅ぼした蘇我氏が権力を握ります。
5~7世紀の政治はこのように、私たちの想像よりはるかに緊迫したものでした。
この時に蘇我氏のバックアップを受けて政治の舞台に登場するのが、日本の古代史で最も有名な人物聖徳太子(厩戸皇子/うまやとのみこ)です。※聖徳太子(しょうとくたいし)は後世の尊称
太子の活躍はちょうど西暦600年ごろから始まり、推古天皇(すいこてんのう)を補佐しながら、冠位十二階、憲法十七条、遣隋使の派遣、仏教の布教などの偉業を次々に実行します。
律令(りつりょう)国家の誕生
聖徳太子が登場するころから、当時のヤマト政権は権力闘争の時代に入りました。
まずは物部氏を滅ぼした蘇我氏が権力を握り、その半世紀後に、今度は天皇家が蘇我氏を滅ぼして権力を取り戻します。
これが古代史を代表する政変である大化の改新(たいかのかいしん)です。
大化の改新
大化の改新は蘇我入鹿(そが の いるか)を暗殺して滅亡させた乙巳の変(いっしのへん、おっしのへん)により始まりました。
その中心になったのは中大兄皇子(なかのおおえのおうじ※のちの天智天皇)と、中臣 鎌足(藤原 鎌足)(なかとみ の かまたり、ふじわら の かまたり)です。
権力の座についた天智天皇は改新の詔(かいしんのみことのり)を発し、都を飛鳥から難波(なにわ)に移転し、白村江の戦い(はくすきのえ・はくそんこう)で唐・新羅連合軍と戦うなどの事跡を残しました。
壬申の乱
天智天皇の死後、その子の大友皇子(おおとものみこ)と、天皇の弟と言われる大海人皇子(おおあまのみこ)との間で、これも古代史最大の戦乱とされる壬申の乱(じんしんのらん)が起こります。
最終的には大海人皇子が勝利を収め、天武天皇として即位することで、天皇を中心とする権力基盤が固まりました。
新しい社会制度の登場
さて、飛鳥時代の最後に日本の社会には大変革が訪れました。
この当時中国を支配していた唐は、現代のアメリカ合衆国に匹敵するほどの超大国であり、東アジアのほとんどの国々はその影響を受けていました。
日本にもさまざまな文化や制度が唐から持ち込まれ、唐の政治制度を参考にした律令政治が導入されました。
701年に文武天皇の治世で制定されたのが大宝律令(たいほうりつりょう)で、律は刑法を表し、令は行政法を表します。
実際に大宝律令の作成に関わったのは、中臣鎌足の子の藤原不比等(ふじわらのふひと)であり、彼がこの時に後の藤原氏による貴族政治を開いたと言えるでしょう。
他にも律令政治では、太政官(だいじょうかん)を中心にした中央集権システムが整備され、豪族たちには官位相当制(かんいそうとうせい)のもとで、階級に応じた官職が定められました。
さらに一般社会では、良民と賤民(せんみん)という身分制度が導入されました。
律令政治はここから平安時代の終わりまで続くことになります。
テストではここがポイント!
飛鳥時代からは、歴史上のできごとや人物がはっきりしてきます。
簡単な歴史年表を自分で作って、そこに年代ごとのできごとや人物を書き込んでみましょう。
それで流れが把握できたら、今度はそこに細かい制度名などを書き加えます。
こうして自分の力で年表を作ることが、歴史に強くなるコツだと言えます。
まとめ
飛鳥時代は法隆寺に代表されるように、何となくゆったりしたイメージがありますが、実際にはドロドロの権力闘争が繰り返された緊迫感あふれる時代だったようです。
その中で聖徳太子、天智天皇、天武天皇などの時代を代表する人物が、歴史を舞台にして活躍していたのです。
しかしこの時代には謎が多く、聖徳太子の実在疑惑を始め、天智天皇と天武天皇は兄弟ではなかったという説や、中臣鎌足は百済の王子だったという説もあります。
日本史の寄り道に、そんな説を調べてみることも面白いでしょう。
受験生、学生、勉強をし直したい社会人の方へ
苦手なこと、一度習ったけどわすれてしまったこと、気になることがあった場合はすぐに学び直すことが重要です!最近では短時間・短期間で学び直しが出来るオンライン家庭教師が人気です。

当サイトでは初めてオンライン家庭教師を利用する方向けに、オンライン家庭教師の選び方を紹介する記事も掲載しておりますので是非ご覧ください!

次の時代を勉強したい方は当サイトのこちらの記事をお読みください ⇒
【日本史勉強法】奈良時代の流れと試験対策のコツ
前の時代を勉強したい方は当サイトのこちらの記事をお読みください ⇒
【日本史勉強法】古墳時代の流れと試験対策のコツ
最後までお読みいただきありがとうございました。