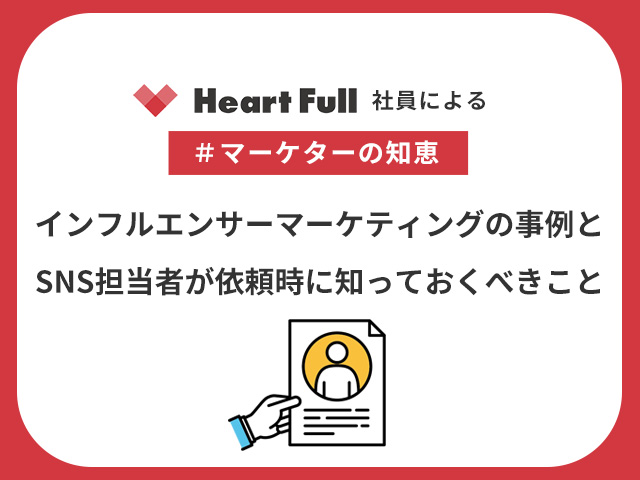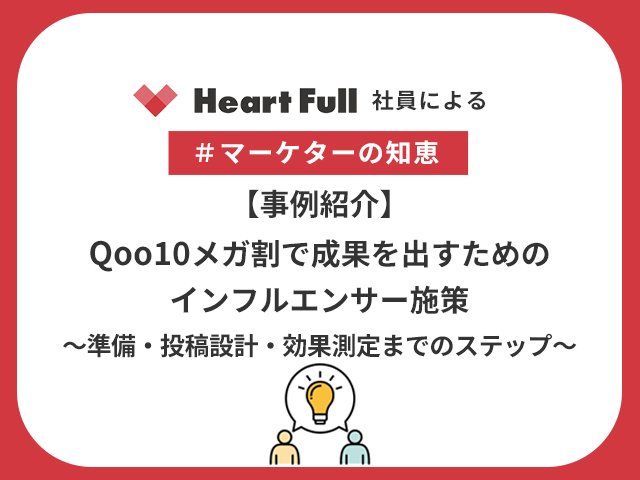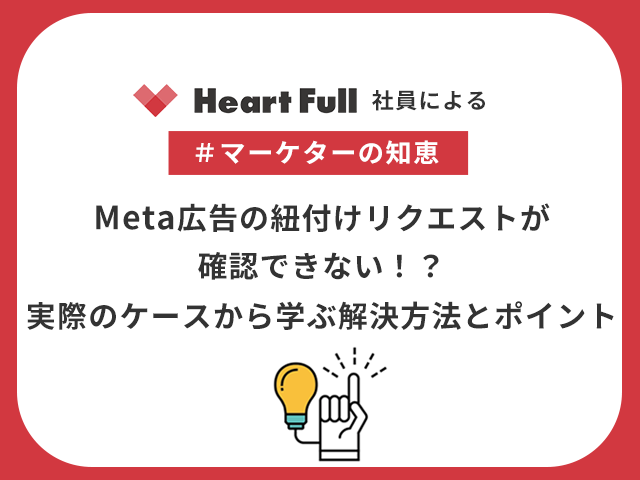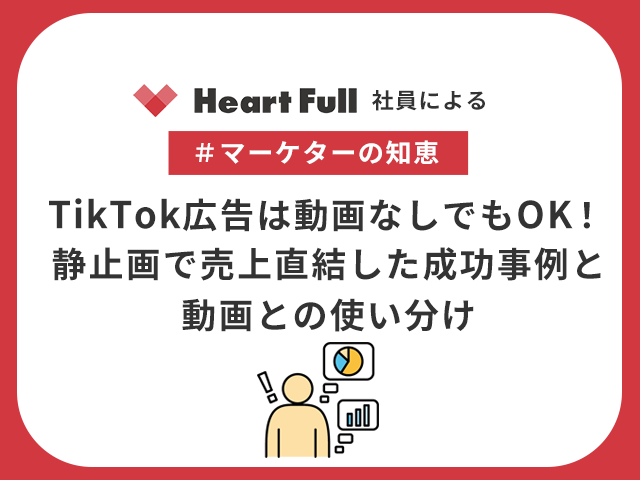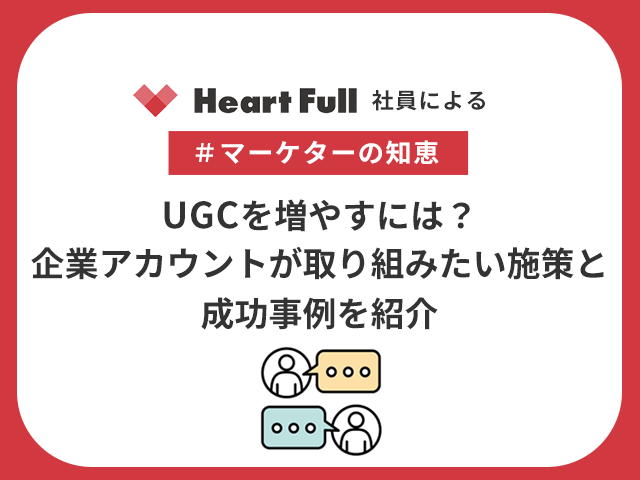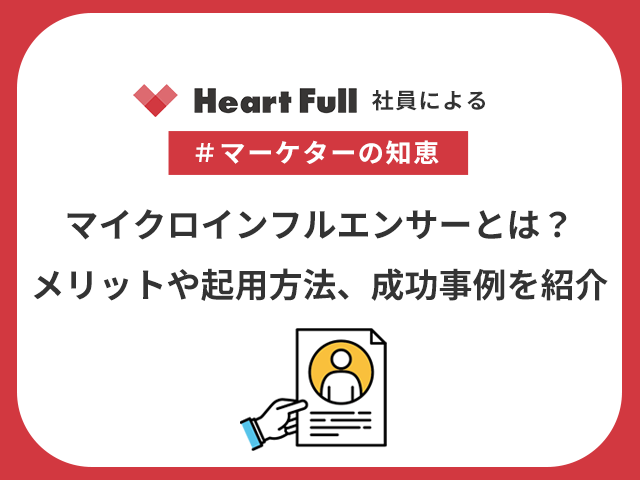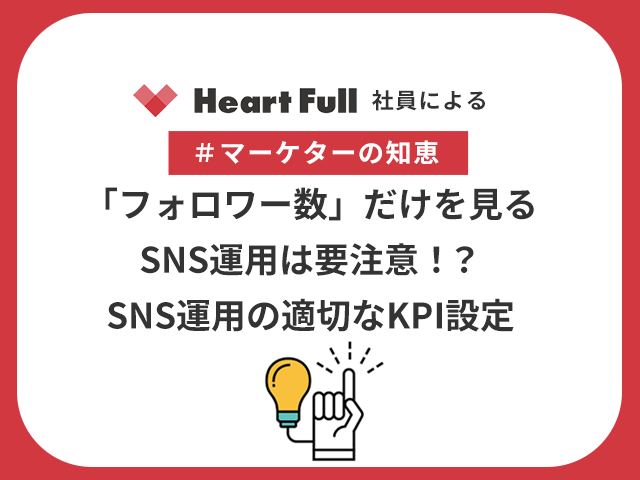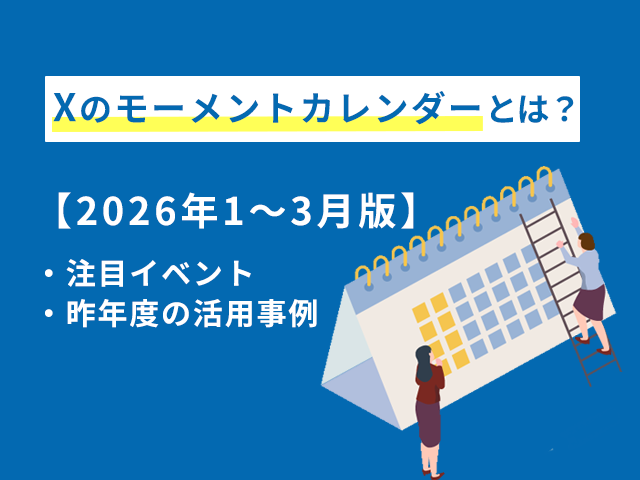インフルエンサーマーケティングは、SNSの普及とともに急速に成長しているマーケティング手法です。
この記事では、実際の事例を交えながら、SNS担当者がインフルエンサーマーケティングを依頼する際に知っておくべき重要なポイントについて解説します。
インフルエンサーマーケティングとは
インフルエンサーマーケティングは、フォロワーを多く持つインフルエンサーの影響力を活用して、商品やサービスをターゲット層に広く認知させる方法です。
一般的に、フォロワー数やエンゲージメント率の高いインフルエンサーに依頼し、口コミ効果によってブランドの認知度を高めたり、エンゲージメントを促進したりすることが目的です。
インフルエンサーは信頼を持たれる存在であり、広告よりも親しみやすいイメージで情報を発信できるため、商品やサービスが自然に消費者の中に浸透しやすい特徴があります。
ターゲット層に効果的にリーチできるという強みから、多くの企業が注目しています。
▼関連記事「インフルエンサーマーケティングとは?気を付ける点や成功のポイントを解説」
ケース1:美容系ブランドのインフルエンサーマーケティング戦略
では実際に、インフルエンサーマーケティングを実施した企業の実例を見ていきましょう。
インフルエンサーマーケティングの成功事例として、まずは美容系グローバルブランドの戦略が挙げられます。この企業では、新商品や新色が出るたびに、インフルエンサーに依頼して商品を拡散させることを行っています。商品を50〜200人規模のインフルエンサーに依頼し、短期間で多くの投稿を拡散させることで、商品の知名度を一気に高める手法を取っています。
特に、大型ECモールのシーズナルセール時期に合わせてインフルエンサーを積極的に起用する傾向があります。このセールは年間を通じて特に重要な販売機会とされており、多くのブランドが認知拡大と売上最大化を目的に、インフルエンサーによるプロモーションを展開しています。
さらに、この企業の特徴的な取り組みとしては、インフルエンサー用に特別な「インフルエンサーセット」を用意することがあります。たとえば、グロスやリップなどの色展開が豊富な商品を詰め合わせて特別セットを作り、インフルエンサーに提供しています。
これにより、インフルエンサー側も商品の紹介意欲が高まり、より質の高い投稿が期待できます。結果として、キャンペーン時のフォロワー増加や投稿のエンゲージメント向上といった効果が見られています。
インフルエンサーの選定については、「この商品ならこの人に合いそうだ」という観点から、インフルエンサーを選定しています。選定方法はジャンルなどによって異なりますが、企業から「この人がいい」「商品がこれで、ターゲットはこの層だから、それに合う人がいい」といった要望がある場合はそれも考慮して選定しますが、フォロワー数が基準となることが多いです。
本事例の全体像について、詳しく知りたい方は下記の資料もぜひご覧ください。
参考資料:『美容系商材で月200名起用!選定→交渉→投稿管理→分析まで支援』インフルエンサーマーケティング事例紹介資料
ケース2:他業界でのインフルエンサーマーケティングの活用事例
インフルエンサーマーケティングは、コスメ業界に限らず様々な業界で活用されています。他にもいくつかの事例を見てみましょう。
食品・アパレル・カフェ
食品やアパレル、カフェの宣伝でもインフルエンサーは力を発揮しています。特に、SNS映えする商品やサービスはインフルエンサーを通じて自然と拡散されることが多く、PR効果が高いとされています。
EC専売品
実店舗がないEC専売品の場合、消費者が実際に商品に触れる機会が少ないため、インフルエンサーのリアルな口コミが重要になります。インフルエンサーを通じて、商品への興味を引き出し、購入へとつなげる施策が多くの企業で行われています。
インフルエンサーマーケティングを依頼する際のポイント
続いて、インフルエンサーマーケティングを依頼する上でのポイントを見ていきましょう。
ターゲットの明確化
インフルエンサーを選ぶ際には、商品やブランドのターゲット層にマッチするインフルエンサーを見極めることが大切です。
20代女性向けのコスメを宣伝する場合には、その層に人気のあるインフルエンサーを起用することで、効果が最大化されます。SNS担当者はフォロワー層やエンゲージメントを基に最適なインフルエンサーを選定することが求められます。
インフルエンサーの選定が難しい場合は、多くのインフルエンサーの中から選定し、投稿の準備や投稿後の分析まで対応してくれる専門業者に依頼するのも一つの方法です。
質重視・量重視の選択
企業の方針によって、フォロワー数や影響力の観点から質を重視するか、拡散数を重視するかの選択が求められます。影響力の大きなインフルエンサー1人に依頼することでブランド価値を高める「質重視」の戦略もあれば、数百人のインフルエンサーに依頼して一気に認知度を上げる「量重視」の戦略もあります。
SNS担当者は、企業の目標に応じてどちらのアプローチが最適かを判断する必要があります。
投稿内容の調整
インフルエンサーに依頼する際は、企業の訴求ポイントを伝えつつも、インフルエンサーが自由に表現できる余地を残しておくことが重要です。型が決まりすぎると、すべての投稿が同じ内容になり、PR感が強くなってしまいます。
そこで、必須の訴求ポイントを指示しつつも、その他の部分はインフルエンサーの独自の表現に任せることで、より自然な投稿に仕上げることができます。
効果測定の難しさ
インフルエンサーマーケティングの効果測定は、ウェブ広告と異なり、売上や直接的なクリック数などが見えにくい部分があります。そのため、KPI(主要業績評価指標)として、認知度の向上やフォロワー数の増加などを設定することが重要です。
また、「どれだけリンクがクリックされたか」「いいね数やシェア数はどうか」といったSNSでの影響力を指標に設定することで、インフルエンサーマーケティングの成果を確認しやすくなります。
下記の記事では、弊社主催のオフラインイベント「LOLLYPOP Meet vol.1 ~インフルエンサーと考える商品の魅力~」で取り上げたテーマ「インフルエンサーマーケティングの効果をどう可視化するか?」について紹介しています。ぜひ参考にしてください。
▼関連記事「【イベントレポート】LOLLYPOP Meet vol.1 ~PR戦略の新たなヒントを探る~」
実施前に確認すべきリスクと注意点
インフルエンサーマーケティングを実施する前に、想定されるリスクや注意点を確認しておくことも重要です。
投稿率の不安定さ
インフルエンサーに依頼しても、全員が必ず投稿するわけではありません。特に、インフルエンサーが商品に満足しなかった場合は、投稿を控えるケースもあります。この点について、SNS担当者は投稿率に変動があるリスクを理解し、インフルエンサー選定時に考慮することが重要です。
顧客の期待値管理
インフルエンサーマーケティングは、直接的な購入につながるケースが見えづらいため、企業側が「効果がなかった」と感じることも少なくありません。SNS担当者は、インフルエンサーマーケティングの目的や期待値を明確にし、社内で「認知度を高める」「フォロワー増加を目指す」といった目標を共有することが重要です。
インフルエンサーマーケティングの新たな活用可能性
インフルエンサーマーケティングは今後も多様な分野で活用されると考えられます。特に、次のようなジャンルでの活用が期待されています。
オンライン診療
オンライン診療(遠隔で医師が診察・相談を行うインターネット利用の医療サービス)など、まだ一般化していないサービスをインフルエンサーが体験し、その内容を発信することで、消費者の関心を引きやすくなります。
スマホを日常的に使用しているSNSユーザー層にとって、オンラインサービスの情報は非常に有益であり、興味を引くコンテンツになり得ます。
EC業界
EC専売の商品は、インフルエンサーによるリアルな使用感が重要な要素となります。特に、消費者が実物に触れることが難しい場合、インフルエンサーの口コミやレビューを通じて、商品の魅力を間接的に伝えることが求められます。
EC専売品において、インフルエンサーマーケティングは今後も効果的なPR手段として活用されるでしょう。
まとめ
インフルエンサーマーケティングは、SNS上での影響力を活かしたマーケティング手法で、商品やブランドの認知度向上に貢献するものです。韓国コスメ会社のような成功事例からもわかるように、インフルエンサーの特性を理解し、適切な戦略を立てることが重要です。
SNS担当者は、インフルエンサーの選定から投稿内容の調整、効果測定までを慎重に行い、期待値を明確にすることで、インフルエンサーマーケティングを有効に活用できるでしょう。ただ、インフルエンサーマーケティングにおいて、「どのインフルエンサーに依頼すべきか分からない」「効果的な施策が立てられない」とお悩みの担当者の方も多いかと思います。
Marketing+Oneを運営しているHeart Fullでは、ニーズに合ったインフルエンサー選定や、戦略立案から効果測定まで、全てのプロセスをサポートいたします。ターゲット層への認知度向上やエンゲージメントの向上を目指し、最適な施策をご提案します。
「インフルエンサーマーケティングをこれから始めたいけど何から着手すればいいか分からない」など、今抱えているお悩みのご相談だけでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。

SNS事例紹介資料を無料配布中!
SNS事例紹介資料をPDF形式で無料でダウンロードいただけます。広告代理店が教えるデジタルマーケティングの基礎を使ってあなたのビジネスの集客アップにご活用ください。